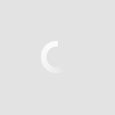投資
貸す
収益還元法で決まるマンション経営の成否
公開日:2015-09-30 00:00:00.0

目次
海外からの不動産投資が盛んな現在、日本の不動産市場のグローバル化は進んでいます。それにつれてマンション経営も収益還元法を重視した経営が不可欠になってきています。
収益還元法とは
「収益還元法」とは、投資対象不動産から生み出される利益を基にその不動産の価格を算出する不動産評価法です。不動産の資産価値を収益性で評価するのが特徴です。
収益還元法は海外では一般的な評価法で、「不動産評価のグローバルスタンダード」と呼ばれています。しかし、日本では従来からあまり普及していませんでした。海外に比べ不動産投資の歴史が浅いことが一因といわれています。
また、日本では不動産仲介会社が「顧客が不動産をいくらで売買したか」を公開しないプライバシー尊重の商習慣が根強く、「取引事例比較法」(※)や「原価法」(※※)が定着しているのも収益還元法の普及を遅らせている要因とみられています。ところが、近年、日本の不動産市場のグローバルな進展に伴い、収益還元法が急速に普及の兆しをみせています。
収益還元法は投資用不動産の物件評価に特に有効です。
また、取引事例比較法や原価法と比べ評価の透明性が高いといわれています。ただし、過去の投資運用履歴とそのデータの信憑性が前提になるので、投資対象不動産の販売会社から提出されたデータの信憑性を精査する必要があります。
収益還元法での評価額の算出法には「直接還元法」と「DCF法」の2つがあります。
●直接還元法
基本的に一定期間(通常は1年)の純収益を投資利回り(還元利回り)で割って評価額を算出する方法です。賃貸マンションなど投資用不動産の物件評価に適しているといわれ、投資利回りが評価のポイントになります。
例えば、投資利回りが5%、年間収益が120万円、年間経費(維持管理費、修繕費、公租公課など)が20万円だった場合でみると、
(120万円-20万円)÷0.05=2,000万円
と、純収益が100万円なので物件評価額は2,000万円になります。
●DCF法
投資対象不動産の保有期間中に得られる純収益を現在評価額に割引計算した額と、保有期間終了時の不動産売却によって得られる予想額(売却予測価格)を、現在評価額に割り戻した額との合算で算出する方法です。
直接還元法より精度の高い評価法ですが、専門的な評価になるので算出はかなり複雑です。日本では1990年代後半から不動産投資プロジェクトの収益分析、不良債権の担保不動産の評価などに利用されています。
直接還元法は賃貸マンションなどの物件評価に適しているのですが、個人投資家などが自分で試算する場合、その評価額はあくまで目安程度に止めておくのが無難でしょう。正確な評価をするためには専門的な知識や計算が必要だからです。
収益還元法は海外では一般的な評価法で、「不動産評価のグローバルスタンダード」と呼ばれています。しかし、日本では従来からあまり普及していませんでした。海外に比べ不動産投資の歴史が浅いことが一因といわれています。
また、日本では不動産仲介会社が「顧客が不動産をいくらで売買したか」を公開しないプライバシー尊重の商習慣が根強く、「取引事例比較法」(※)や「原価法」(※※)が定着しているのも収益還元法の普及を遅らせている要因とみられています。ところが、近年、日本の不動産市場のグローバルな進展に伴い、収益還元法が急速に普及の兆しをみせています。
収益還元法は投資用不動産の物件評価に特に有効です。
また、取引事例比較法や原価法と比べ評価の透明性が高いといわれています。ただし、過去の投資運用履歴とそのデータの信憑性が前提になるので、投資対象不動産の販売会社から提出されたデータの信憑性を精査する必要があります。
収益還元法での評価額の算出法には「直接還元法」と「DCF法」の2つがあります。
●直接還元法
基本的に一定期間(通常は1年)の純収益を投資利回り(還元利回り)で割って評価額を算出する方法です。賃貸マンションなど投資用不動産の物件評価に適しているといわれ、投資利回りが評価のポイントになります。
例えば、投資利回りが5%、年間収益が120万円、年間経費(維持管理費、修繕費、公租公課など)が20万円だった場合でみると、
(120万円-20万円)÷0.05=2,000万円
と、純収益が100万円なので物件評価額は2,000万円になります。
●DCF法
投資対象不動産の保有期間中に得られる純収益を現在評価額に割引計算した額と、保有期間終了時の不動産売却によって得られる予想額(売却予測価格)を、現在評価額に割り戻した額との合算で算出する方法です。
直接還元法より精度の高い評価法ですが、専門的な評価になるので算出はかなり複雑です。日本では1990年代後半から不動産投資プロジェクトの収益分析、不良債権の担保不動産の評価などに利用されています。
直接還元法は賃貸マンションなどの物件評価に適しているのですが、個人投資家などが自分で試算する場合、その評価額はあくまで目安程度に止めておくのが無難でしょう。正確な評価をするためには専門的な知識や計算が必要だからです。
マンション経営は収益還元法で行う時代へ
近年、日本の不動産市場のグローバルな進展に伴い、国内には海外資金が大量に流入しています。2014年末現在の海外企業や海外投資ファンドによる国内不動産取引額は約1兆円に達し、 国内不動産総取引額の約2割を占めています。
その影響で不動産評価法も旧来の取引事例比較法や原価法から透明性の高い収益還元法に転換せざるを得ず、今後は日本でも収益還元法が不動産評価のスタンダードになるとみられています。その結果、投資用不動産の評価額も投資利回りで決まる時代がやってきそうです。
これは、マンション経営をしている投資家には、その資産価値を維持しようとすれば「空室を出さない努力」や「家賃を下落させない努力」が厳しく求められる時代になってきたことを意味します。
そのためには経営しているマンションの管理や修繕を徹底し、入居者に住みたいと思ってもらえるような物件にする必要があります。ある程度の追加投資も求められます。
追加投資を惜しまず適切な修繕を施しているマンションと、経費削減のために必要な追加投資を怠ったマンションとでは、必然的に家賃収入や入居率に差が出ます。空室率の増加や家賃の下落で収益性が低下した賃貸マンションは、収益還元法では評価額が低くなり、売却時には大赤字になる可能性があります。
例えば、家賃純収益が年間1,200万円の賃貸マンションを8%の投資利回りで収益還元すると、物件評価額は1億5,000万円になります。しかし、物件への追加投資を怠り、10年の間に家賃純収益が例えば20%減少したとすると、物件評価額は1億2,000万円に下落します。
これとは逆に、適切な追加投資により家賃純収益の減少幅が5%で済めば、物件評価額は1億4,250万円となり、下落額はわずか750万円に止められます。このように、マンション経営の収益額を具体的に把握できるのも、取引事例比較法や原価法にない収益還元法のメリットです。
収益還元法に基づきマンション経営をすれば、投資の収益性を見える化できるので「空室を出さない努力」や「家賃を下落させない努力」に敏感にならざるを得ません。資産価値を維持するための追加投資額も概算できるでしょう。マンション経営の投資手法もグローバルスタンダード化しています。
________________________________________________________
(※)「取引事例比較法」……投資対象不動産周辺の不動産取引事例を参考に評価額を算出する方法
(※※)「原価法」……対象不動産評価時点において、新しい不動産を購入する場合の原価により評価額を算出する方法
その影響で不動産評価法も旧来の取引事例比較法や原価法から透明性の高い収益還元法に転換せざるを得ず、今後は日本でも収益還元法が不動産評価のスタンダードになるとみられています。その結果、投資用不動産の評価額も投資利回りで決まる時代がやってきそうです。
これは、マンション経営をしている投資家には、その資産価値を維持しようとすれば「空室を出さない努力」や「家賃を下落させない努力」が厳しく求められる時代になってきたことを意味します。
そのためには経営しているマンションの管理や修繕を徹底し、入居者に住みたいと思ってもらえるような物件にする必要があります。ある程度の追加投資も求められます。
追加投資を惜しまず適切な修繕を施しているマンションと、経費削減のために必要な追加投資を怠ったマンションとでは、必然的に家賃収入や入居率に差が出ます。空室率の増加や家賃の下落で収益性が低下した賃貸マンションは、収益還元法では評価額が低くなり、売却時には大赤字になる可能性があります。
例えば、家賃純収益が年間1,200万円の賃貸マンションを8%の投資利回りで収益還元すると、物件評価額は1億5,000万円になります。しかし、物件への追加投資を怠り、10年の間に家賃純収益が例えば20%減少したとすると、物件評価額は1億2,000万円に下落します。
これとは逆に、適切な追加投資により家賃純収益の減少幅が5%で済めば、物件評価額は1億4,250万円となり、下落額はわずか750万円に止められます。このように、マンション経営の収益額を具体的に把握できるのも、取引事例比較法や原価法にない収益還元法のメリットです。
収益還元法に基づきマンション経営をすれば、投資の収益性を見える化できるので「空室を出さない努力」や「家賃を下落させない努力」に敏感にならざるを得ません。資産価値を維持するための追加投資額も概算できるでしょう。マンション経営の投資手法もグローバルスタンダード化しています。
________________________________________________________
(※)「取引事例比較法」……投資対象不動産周辺の不動産取引事例を参考に評価額を算出する方法
(※※)「原価法」……対象不動産評価時点において、新しい不動産を購入する場合の原価により評価額を算出する方法
編集監修者情報