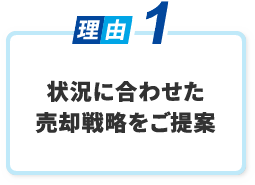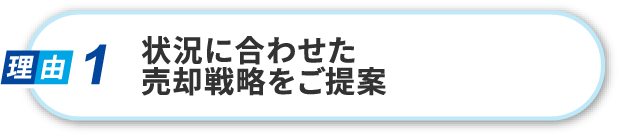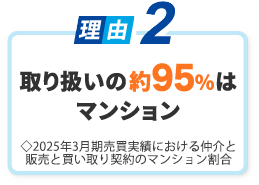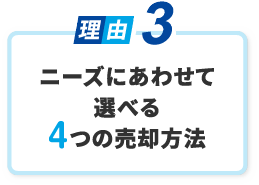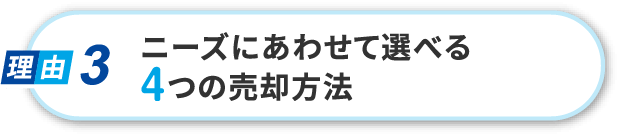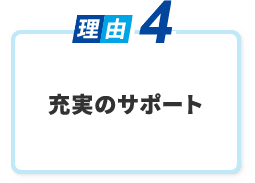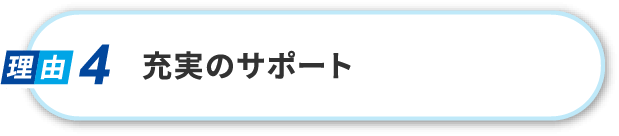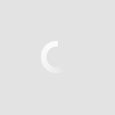マンションの相続税はどれくらいかかる?計算方法や控除について

先読み!この記事の結論
- マンションの相続の手続きの流れを紹介
- マンションの相続税の計算方法を紹介
- 相続したマンションの活用方法や注意点を理解できる
こんな悩みの人にピッタリ
- マンションの相続税について知りたい
- マンションの相続税について相談できる専門家が知りたい
目次
マンション相続の手続きの流れ
これまで相続の経験が無い方は、自分が相続を行う立場になると困惑してしまうこともあるでしょう。多くの方は相続についての知識や経験が無いため、当然のことだと思います。
しかし、全く知識が無いまま相続を進めると、後々のトラブルになりかねません。事前に大まかな手続きの流れや、具体的に何を行うのかについておさえておくことが大切です。
マンション相続に必要な手続きのおおまかな流れについては次のようになっています。
1.相続人調査・相続財産調査
2.遺産分割協議
3.所有権移転登記による名義変更
4.相続税の申告
それぞれについて、以下ではステップごとに解説していきます。
手続きの流れ
1.相続人調査・相続財産調査
まず初めに、相続人調査と相続財産調査を行う必要があります。相続人調査では「相続人は誰か・何人いるか」を調べ、相続財産調査では「何が相続財産なのか」を調べます。
法定相続人が複数人いる場合、遺産の分割について相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。ただ、遺族が把握していない財産や相続人が後から発覚することも少なくありません。
後から相続財産などが新しく発見された場合、これまでの協議内容を白紙にすることもあります。また、異なった事実が遅れて判明すれば、トラブルに発展することもあるでしょう。
そのようなことにならないためにも、この相続人調査と相続財産調査をしっかりと行う必要があります。
2.遺産分割協議
上記でも記載したように、複数人の法定相続人がいる場合には遺産分割協議が行われます。相続人全員で話し合い、どのように分割するかについて協議することになります。
現金であれば相続人それぞれに金額を分配し、不動産などは細かな事項までを検討して遺産分割を進めます。
3.所有権移転登記による名義変更
遺産分割協議を行い、マンション相続人となればマンション名義を変更する必要があります。所有権が被相続人から相続人へ移ったことを明確にするための登記が「所有権移転登記」です。
この登記に期限は設けられていませんが、行っていなければマンションの売却などができません。そのため、相続が決まればできるだけ早急に所有権移転登記を行う必要があるでしょう。
4.相続税の申告
最後に相続税を申告することも忘れてはいけません。ただし、基礎控除が存在しており遺産総額が控除内であれば相続税がかからないため注意が必要です。基礎控除額については以下の式で計算することができます。
3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
相続財産の合計が基礎控除を下回れば申告の必要はありませんが、上回れば申告が必要です。
マンションの相続で発生する相続税とは?
マンションの相続を行う際にはその計算方法や評価方法などをおさえておく必要があります。以下で具体的に解説していきます。
そもそも相続税とは
相続税とは、相続や遺贈で引き継いだ遺産総額が基礎控除を超える場合に、その超える部分に課せられる税金です。上記でも記載したように、基礎控除額を超える場合には金額に応じた相続税を支払う必要があります。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際の基準になる課税価格です。相続税を計算するには財産の価値を調べる必要があります。相続税の申告を行う際には、財産を「相続税法」や、この「相続税評価額」を基礎として申告することになります。
マンションの相続税評価額の計算方法
・マンション全体の相続税評価額に持分割合をかける
マンションの相続税評価額の計算方法は少し複雑です。マンションでは、専有部分(自分の部屋など)と共有部分(廊下やバルコニーなど)が存在しています。マンションの相続税を評価する場合、この共有部分も含める必要があります。
共有部分を含めた計算は、マンション全体の相続税評価額を出し、それに持分割合をかけます。持分割合とは、マンション全体に対し自分が所有する専有部分の割合です。このように計算することで、共有部分を含めた相続税評価額を算定できます。
持分割合は区分所有建物の登記簿や売買契約書に記載されているので確認するようにしましょう。
・マンションの相続税評価は土地と建物を分ける必要がある
持分割合の確認ができれば、次は相続税の評価額を計算します。相続税の評価としては土地と建物を分けて考える必要があるのです。それぞれの評価方法も細かく規定されているため、あらかじめ把握しておく必要があるでしょう。
以下ではマンションの土地部分の評価方法と建物部分の評価方法について記載していきます。
マンションの土地部分の評価方法
土地の相続税評価額については路線価方式と倍率方式の2種類があります。詳細は次の通りです。
・路線価方式
市街地であれば、路線価方式で計算する必要があります。路線価とは、道路に面した土地に認定された1平方メートルあたりの評価額です。この方式でマンション全体の相続税評価額を出す場合、計算式は次のようになっています。
路線価×地積×画地補正率
なお、地積は土地の面積を表し、画地補正とは道路や土地の形を考慮して微調整を行うことを意味しています。
・倍率方式
倍率方式は路線価が定められていない土地に適用する相続税評価方法です。固定資産税評価額に評価倍率を掛け合わせ、相続税評価額を計算します。なお、倍率とは各地域で認定される評価倍率を表します。この方式でマンション全体の相続税評価額を出す場合、計算式は次の通りです。
固定資産税評価額×倍率
例えば、固定資産税評価額が300万円で評価倍率が1.5倍の場合、相続税評価額は450万円となります。
マンションの建物部分の評価方法
・建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額と同じ
マンションの建物部分の相続税評価額については、固定資産税評価額と同様となっています。建物の固定資産税評価額については建物それぞれで算定されているため、確認することが可能です。
・固定資産税評価額の確認の仕方
固定資産税評価額の確認方法は次の2つです。
1.課税証明書によって確認する
2.役所にて固定資産税評価額を入手する
課税証明書では「家屋の所在」の「固定課税標準額」を見れば、所有するマンションの評価額が確認できます。また、固定資産税評価額を入手する際は、基本的に関係者だけしか取得できないため注意が必要です。(ただし、司法書士に依頼した場合は入手可能)
マンション相続で活用できる特例や控除
マンション相続を行う際に特例や控除を利用すれば、税金を抑えることができます。
ただし、相続人自身が申告する必要があるため、どのようなものがあるのか把握しておきましょう。
・基礎控除
相続税には基礎控除があります。上記でも示した通り、
3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
の計算式で算定することができます。例えば、夫が亡くなり、妻と子供1人が残された際は基礎控除が4200万円となります。遺産総額が基礎控除額を超えない場合には相続税が課税されず、申告も不要です。
・配偶者控除
この他にも、被相続人の配偶者であれば配偶者控除によって税金を軽減することができます。ただし、この制度では配偶者が相続した遺産額が1億6,000万円または、配偶者の法定相続分
のどちらか大きい金額までは課税されないこととなっています。
・特例制度
この他にも、マンション相続では相続する土地の評価を下げることで「小規模宅地等の特例」を利用できます。
この制度を利用すれば配偶者や同居人がマンションを引き継ぐ場合、土地面積330平方メートルまで80%の減額が可能です。ただし、「相続する人がそのまま住むこと」と「同居していたこと」の両方を満たす必要があります。
マンションの相続税のシミュレーション
例えば、妻と子供2人に対しマンションを含む遺産総額が100,000,000円あったとします。ここから基礎控除である48,000,000円を差し引き52,000,000円が課税遺産総額です。仮に妻が26,000,000円、子供がそれぞれ13,000,000円を相続したと想定しましょう。その場合、相続税は以下のようになります。
配偶者 26,000,000円×税率15%-控除額500,000円=3,400,000円
子供① 13,000,000円×税率15%-控除額500,000円=1,450,000円
子供② 13,000,000円×税率15%-控除額500,000円=1,450,000円
このことから、相続税の総額は6,300,000円となります。
ただし、実際に負担することになる相続税は相続割合によって決定します。もし、相続割合が、妻50%・子供①30%・子供②20%と想定した場合、以下のような相続税となります。
妻:3,150,000円
子供①:1,890,000円
子供②:1,260,000円
しかし、配偶者控除を利用できる妻には3,150,000円の税金がかからないのです。このような控除を利用すれば、税金を抑えることにつながります。
マンションの相続で相続税以外にかかる費用
マンションの相続では、相続税以外にも必要になる費用があります。例えば、相続登記においては登録免許税が必要になります。こちらは「固定資産税評価額×0.4%」で計算を行いましょう。
また、税金面や法律について専門家に依頼する場合にも別途費用が掛かります。一般的に、これらの費用は相続財産額の0.5%~1%とされています。
相続が発生した場合の登記手続きなどは自分でもできる?
相続が発生した場合の登記ですが、自分で行った場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下では自分で手続きをする場合と専門家に依頼する場合それぞれのメリット・デメリットを解説します。
自分で手続きをする場合と専門家に依頼する場合について
・相続に関する手続きを自分で行う場合のメリット
相続に関する手続きなどを自分で行うメリットは、司法書士や弁護士などに支払う費用が掛からないことです。相続税の手続きは専門性が求められ、支払う報酬も高額になる場合もあります。
また、遺産総額に応じた額を支払うことも多く、遺産総額が多ければそれだけ高くなるのです。このような費用が掛からないことはメリットと言えるでしょう。
・相続に関する手続きを自分で行う場合のデメリット
自分で手続きを行う際のデメリットは相続に関する法律を理解しておかなければならないことです。相続に関する手続きは様々な法律や通達などを正しく解釈しなければならないことも多数あります。
このようなことを正しく理解し、正確に処理を行わなければならないことはデメリットと言えます。
・専門家に依頼する場合のメリット
専門家に依頼するメリットは、自分で行う場合と比較して正確な処理を行ってもらえることです。法律や税金の専門家に依頼すれば、プロが責任を持って処理を行ってくれるため、安心して手続きを進められます。
・専門家に依頼する場合のデメリット
上記にも記載した通り、コストが必要になることはデメリットと言えるでしょう。専門的な知識をもとに処理を行ってもらえる反面、それに応じた料金を支払う必要があります。
相続に関する相談ができる専門家
相続に関する相談が行える専門家は以下の通りです。
・司法書士
・弁護士
・税理士
・行政書士
ただし、相談内容によって相談すべき専門家も異なります。相続や抵当権の抹消などであれば司法書士、税金面のことは税理士という形で使い分けることが大切です。事前に相談したい内容を整理しておき、どの専門家に相談すべきかを考えた上で利用するようにしましょう。
マンションを相続した場合の活用方法と注意点
マンションを相続した場合、様々な活用方法があります。主な活用法としては次の3つが挙げられるでしょう。
1.住む
2.貸す
3.売る
それぞれについて理解しておけば、相続したマンションを有効に活用することが可能です。以下ではこれらの活用法のメリット・デメリットや、相続に関する注意点を解説していきます。
相続したマンションの活用方法
・住む場合のメリット
相続したマンションに住む場合、自分が育った家や思い入れのある実家を残せるメリットがあります。これまでの思い出を残したい方であれば、相続してそのまま住むことも選択肢の一つでしょう。
・住む場合のデメリット
相続したマンションに住む際のデメリットは、当然ですが、間取りや部屋の広さを選べません。物件を選ぶことはできないため、好みの部屋に住めない点はデメリットであると言えるでしょう。
・貸す場合のメリット
相続したマンションを貸し出すことで、家賃収入を得ることも可能です。継続して入居者がいれば、収入が得られるのは大きな魅力でしょう。
・貸す場合のデメリット
マンションによっては、賃貸に向いていないこともあります。例えば、ファミリータイプのマンションなどは、居住目的の売買に向いているので、売却した方が有利になることもあるのです。
また、数年先に自分が住みたいと考えている場合にも、デメリットになる可能性もあります。一度貸してしまえば立ち退きしてもらうのは難しいため、将来自分が住みたい場合は慎重に考えましょう。
・売却するメリット
売却するメリットとしては、現金化することでまとまった資金を得られることでしょう。相続人同士で分配することもでき、無駄な争いを行わずに済みます。また、現金化することで相続税の支払いを行うことも可能です。
・売却するデメリット
これまで自分が生まれ育ったマンションを他人に譲ることは、デメリットと言えます。様々な思い出があり、手放したくない場合には売却せずに他の方法を考えた方が良いでしょう。
分譲マンションの相続に関する注意点
・どうするかしっかりと計画する
マンションを相続した際にはどのように処理するかを入念に計画しましょう。上記に記載したように、売却するのか、住むのか、貸すのかなどをはっきりと決めることが大切です。
また、親族間でもマンションの処理についてはよく協議する必要があります。曖昧な状態で相続を進めると、後々のトラブルにつながるため注意しましょう。
・売却する際には複数の会社に査定してもらう
売却するのであれば、必ず複数の会社に査定してもらいましょう。不動産会社によって査定額が異なる場合が多く、相場を見極めるためにも複数社に依頼することが大切です。納得できるような金額を提示してくれた会社に売却するようにしましょう。
・絶対に放置しない
マンションを相続した際に、最もやってはいけないことは放置することです。不動産は、所有しているだけでも税金が発生します。マンションであれば、その上で維持費も発生するため、放置していれば費用だけが発生する状態になるのです。そのため、むやみに放置しておくことだけは避けるようにしましょう。
まとめ
マンションの相続においては分配することが難しく、トラブルも発生しやすいです。事前に遺産整理を行っていなければ、相続人の間でもめてしまうことも少なくありません。
そのようなことにならないためにも、専門家の意見を聞いたり、計画的に相続を進めることが大切です。上記のことを参考にして、慎重に相続を進めるようにしましょう。