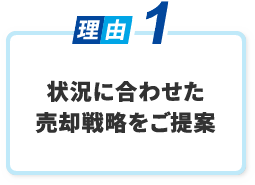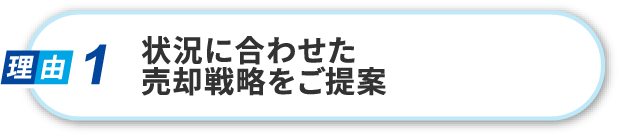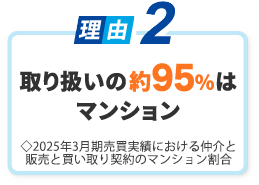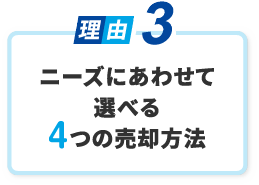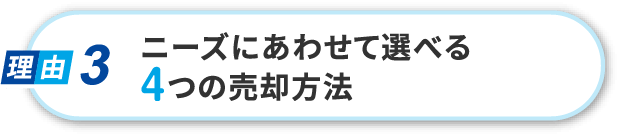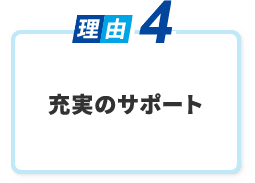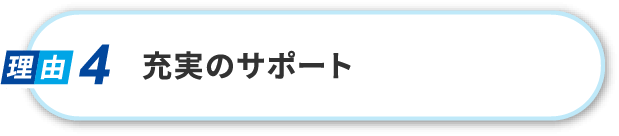変わってきたマンション住み替えの目的

目次
マンションを住み替えるといえば、かつては就職、結婚、転勤、子供の増加などライフステージの変化への対応が目的でした。ところが国土交通省が今年9月に発表した「平成25年住生活総合調査(確報集計)結果」によると「親、子などとの同居・隣居・近居」を目的としたマンションなどの住居住み替えが平成20年の前回調査時と比べて倍増していることが分かりました。このことが関係者の注目を集めています。
住生活総合調査が示すマンションなどの住み替え目的の変化
調査によると、「最近5年間の住み替え・改善の実施状況」では、住み替えを行った世帯が19%、住み替えをせず住宅リフォームを行った世帯が21%、住宅を建て替えた世帯が0.8%、何もしなかった世帯が52%となっています。
そして「最近5年間に実施した住み替えの主な目的」は「就職、転職、転勤などに対応」が21.7%で「親、配偶者などの世帯からの独立」の21.2%とほぼ同数で1、2位を分け合っています。これに「子育て・教育の環境を整える」と「住宅を広くする、部屋を増やす」が17.7%、「通勤、通学などの利便の向上」が13.4%、「親、子などとの同居・隣居・近居」が10.5%と続いています。
これらの経年変化を見ると、「住宅 を広くする、部屋を増やす」は昭和 58 年 調査では33.4%だったので、過去30年間でほぼ半減しています。「就職、転職、転勤などに対応」も昭和58年調査では25.9%、昭和63年調査では28.4%だったのが、今回調査では21.7%と、これも減少の傾向にあります。
一方で「親、子などとの同居・隣居・近居」は平成5年調査の4.1%から漸増し、今回の調査では前回調査の5.3%から倍増、さらに「今後5年以内の住み替え・改善意向の主な目的」でも17.8%と、今後も増加していきそうな傾向を示しています。
親子の同居・隣居・近居の増加予想は「長子の年齢別に見た今後5年以内の住み替え・改善意向」からも推測できそうです。
同項目の調査結果では、長子の年齢が低い世帯層ほど住み替え意向が強く(長子5歳以下32.8%、長子6~11歳18%、長子12~17歳11.3%)、「親と子からなる世帯の住み替えの目的」は「子育て・教育の環境を整える」が最多の32.9%、次いで「住宅を広くする、部屋を増やす」27.7%、3位「親、子などとの同居・隣居・近居」17.7%と続いています。
かつて住み替え目的の上位を占めていた「就職、転職、転勤などに対応」は12.4%、「通勤、通学などの利便の向上」は9%にそれぞれ後退しており、親子の同居・隣居・近居の増加ぶりを印象づける結果ともなっています。
不動産関係者の中からは「住み替え目的トップの『子育て・教育の環境を整える』と、同3位の『親、子などとの同居・隣居・近居』はリンクしている」という声も聞かれます。
高まるマンションの「同居・隣居・近居ニーズ」
実際のところ、親子の同居・隣居・近居ニーズを反映してか、最近はこれを目的とした住み替えを助成することで、他地域からの住民の流入を図る自治体が増加しています。
例えば、東京都北区は「親世帯が10年以上区内に住んでおり、子世帯が親世帯と同一地域内で住宅を購入する場合、20万円を上限に不動産登記費用を助成」、神戸市は「市内に1年以上居住している親世帯の近くに子世帯が住む場合、20万円を上限に引っ越し費用、不動産登記費用などを助成」という施策を打ち出しています。
また、集合住宅であるマンションの特徴を生かし、親世帯と子世帯が同一マンション内に住む「マンション内隣居・近居」も年々増加しているといわれています。
近年は現役を引退してから趣味や旅行を存分に楽しみ、マイペースで第二の人生を送りたいとする「アクティブシニア」が増えています。彼らにとって、子世帯と適度なプライバシーと距離感を保ちつつ、いざ何かあった時にはすぐに助け合える「マンション内隣居・近居」は最適な居住形態ともいえます。
今回の調査は今後、親子の同居・隣居・近居に配慮したマンションニーズが高まるということを示していると考えられるでしょう。