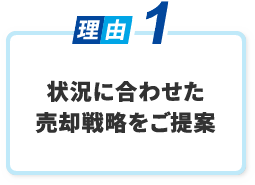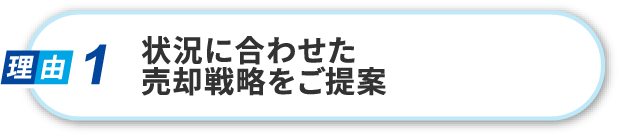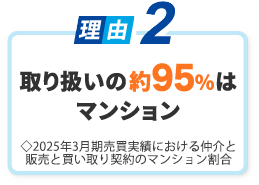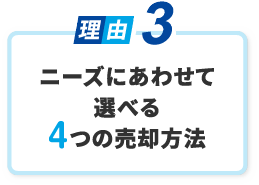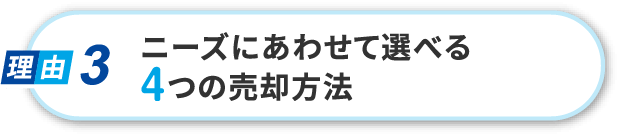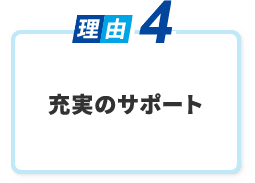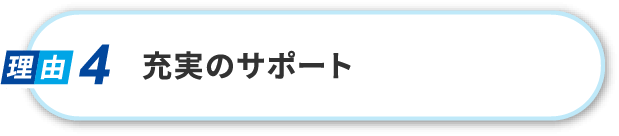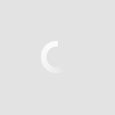マンションの売却費用はどれくらい?仲介手数料や税金を抑えるには?

先読み!この記事の結論
- マンションを売却したらどのような費用や税金が必要か
- 仲介手数料はどうして必要で、どのくらいかかるのか
- 税金はどのくらいかかり、節税できるのか
こんな悩みの人にピッタリ
- マンション売却を本気で考えている方
- どのくらいの費用を見積もっておけばいいのか知りたい方
目次
マンション売却にかかる費用は?
マンションを売却すると次のような手数料や税金が必要になります。
●仲介手数料
●印紙税
●ローンの一括返済のための事務手数料
●登記費用
●所得税・住民税・復興所得税
●引越し代・ハウスクリーニング代などのその他費用
それぞれの費用の詳細について詳しく見ていきましょう。
マンション売却時の仲介手数料
マンションを売却した時に、支払金額が大きい費用は仲介手数料と所得税などの税金です。まずは仲介手数料について詳しく解説します。
マンションを売却する時には、通常は不動産会社に仲介を依頼して購入者を探すことになります。売買契約成立時に不動産会社に、手数料として支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料が必要な理由
不動産会社を利用せずに、自分で購入者を見つけて、売買契約書を交わすことができれば、不動産会社に仲介を依頼する必要はないので、仲介手数料の支払いも必要ありません。
しかし、現実問題として、不動産業界に携わっている人でなければ、自分で購入者を探したり、法的に効力のある契約書を作成して交わすことは難しいものです。また、買主さまがローンを利用する場合、金融機関に重要事項説明書を提出しなければ、なりません。
このような観点から通常は、マンションを売却したい時には不動産会社に仲介を依頼して、購入者を探してもらいます。また、契約前の購入者への説明も宅地建物取引士の資格を持ったスタッフにしてもらいます。
仲介手数料は、購入者を探してもらったり、契約を購入者と結ぶための書類作成や手続きを代行してもらうための手数料として必要です。マンションを売却するときには、必要不可欠な費用の一つと考えていいでしょう。
仲介手数料は宅地建物取引業法で売却金額に応じて上限額が次のように定められています。
●200万円以下の部分:売却価格の5% + 消費税
●200万円超から400万円以下の部分:売却価格の4% + 消費税
●400万円を超える部分:売却価格の3% + 消費税
仲介手数料はいつ支払う?
仲介手数料は成功報酬です。成功報酬なので、支払うタイミングは売買契約が成立した時です。不動産会社によっては、契約書を交わした時点で仲介手数料の半額の支払いをして、残りは引渡しが完了した時点での支払いという会社や、引渡しが完了した時点で全額の支払いという会社もあります。
仲介を依頼するための契約を媒介契約と言いますが、媒介契約を結ぶだけでは手数料は一切発生しません。売却できずに媒介契約を終了する場合には、その不動産会社には仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介手数料は安くしたいけど
もしも3,000万円でマンションを売却した場合には、消費税10%で仲介手数料の上限金額を支払うと、105.6万円になります。
仲介手数料がかなり高額になることに驚く方もいることでしょう。できることなら、仲介手数料も安くすませたいと考える方が多いでしょう。マンションを売却する時の仲介手数料を解説します。
仲介手数料は、値引きしてもらった方がいい?
媒介契約を結ぶ時に、不動産会社に対して仲介手数料の値引き交渉をする人もいますがおすすめできません。
上限はあるけれど、下限はないのが仲介手数料の特徴です。不動産会社は利益を出すために、宅地建物取引業法で定められた上限を超えないギリギリのラインで仲介手数料を設定します。
下限がないのであれば、仲介手数料を値引きすることは可能なのか気になる人もいるでしょう。結論から言うと値引き交渉をすることは可能ですが、値引きをすることで必ずしも結果が伴うかどうかが問題です。
ここで注目してほしいのが、「手取り金額」です。たとえば、仲介手数料を半額にしてくれる会社と媒介契約を締結し、3,000万円で売却ができ、仲介手数料52.8万円を支払うのと3,100万円円で売却でき、上限の仲介手数料108.9万円を支払うのでは、手取り額が多いのは3,100万円で売却したケースです。確かに仲介手数料が安いのは魅力に見えますが、必ずしも最善の結果になるとは限らないことを覚えておきましょう。
仲介手数料の値引き交渉をするよりも、適切な仲介手数料を払って、適切な広告宣伝をしてもらい、不動産を少しでも高く売却することを考えたほうが結果として好条件となる可能性が高いでしょう。
マンション売却でかかるその他の費用
仲介手数料以外でマンションを売却した時に必要になる費用について詳しく見ていきましょう。
●印紙税
印紙税とは、契約書や、株券などの金融商品の証券などに収入印紙を購入して貼り付けることで納税する税金です。不動産売買では、売買契約書に記載される金額に応じて定められた額面の収入印紙を、売買契約書に貼り付けて納税します。納税額は200円から60,000円程度です。
●ローンの一括返済のための事務手数料
マンションを売却した金額で、住宅ローンを一括返済した時には、金融機関で一括返済の手続きを行うための事務手数料が必要です。金額は金融機関によって異なりますが、通常は10,000円から30,000円の範囲内です。正確な金額は、ローンの借り入れをしている金融機関にお問い合わせください。
●登記費用
登記とは、不動産などの固定資産の名義人を法務局に登記して、権利関係を明確にするものです。不動産を売買した時には、不動産の所有者が変わるので、所有権移転登記が必要です。しかし、通常は所有権移転登記の費用は買主さま側の負担になるので、売主さま側には必要ありません。
売主さま側が負担しなければいけない登記費用は、抵当権抹消登記のための費用です。売却金額でローンの一括返済をする時には、ローンの借り入れをしていた金融機関が設定した抵当権を外す必要があります。
抵当権を外すための抵当権抹消登記は、売主さまの負担になります。抵当権抹消登記のための登録免許税は不動産1筆につき1,000円です。土地と建物のそれぞれに対して必要です。土地1筆と建物1筆の場合には合計2件で2,000円です。
また、抵当権抹消登記は司法書士へ依頼した場合には、司法書士への報酬も必要です。抵当権抹消登記の報酬は一般的に20,000円から25,000円程度です。
●所得税・住民税・復興所得税
マンションを売却したことで譲渡益が出た場合には、この3つの税金が課税されます。税金の詳細については後述します。
●引越し費用・ハウスクリーニング費用などのその他費用
自宅マンションを売却する場合には、新居への引越しが必要になります。新居を用意したり、引越し業者を依頼する費用などが必要になります。また、必要に応じてハウスクリーニングを入れることがあります。
マンション売却で譲渡益が出た場合にかかる費用
マンションの売却で、譲渡益が出た場合にだけ発生する費用があります。
所得税と住民税、復興所得税の3つの税金です。この3つの税金は、売却金額から取得費と売却にかかった費用を差し引いた残りの金額がプラスになった場合に課税されます。売却金額自体に課税されるものではない点に注意しましょう。
取得費とは、マンションを購入した金額から減価償却費を差し引いた金額と、取得にあたってかかった手数料などの費用の合計です。マンション購入時の契約書や領収書など、証明できる書類があれば取得費として計上できます。取得費の証明ができない場合には、売却金額の5%が取得費となります。
税率は所有期間によって5年を超える所有の長期譲渡所得と、5年以下の所有の短期譲渡所得とそれぞれ次のように定められています。
長期譲渡所得の場合は、譲渡所得に対して所得税は15%、住民税は5%、復興所得税は0.315%(所得税×2.1%)の合計税率20.315%です。短期譲渡所得の場合は、譲渡所得に対して譲渡所得税は30%、住民税は9%、復興所得税は0.63%(所得税×2.1%)の合計税率39.63%です。
これらの税金は、マンションを売却した翌年に確定申告をして支払います。確定申告を忘れると、延滞税など本来支払わなくてもいい金額が加算されてしまうので注意しましょう。
マンション売却の際に戻ってくるお金
マンションを売却すると、手元に戻る費用として次のようなものがあります。
●住宅ローンの保証料の返戻金
住宅ローンを借りる時に、万が一に備えて保証会社と契約する場合があります。マンションを売却したことでローンを完済した場合には、契約している残りの期間の保証料が返戻金として戻ってきます。ただし、期間に応じた割合で戻ってくるわけではありません。あらかじめ金融機関に確認しておくとよいでしょう。
●火災保険料の返戻金
火災保険料を5年や10年という単位で長期間支払っていた場合には、契約期間の残りの部分の保険料が返戻金として戻ってきます。ただし、保険会社にはマンションを売却したことは伝わらないので、返戻金を戻してもらうためには、自分から保険会社に連絡する必要があります。
●固定資産税・都市計画税の精算金
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日の所有者に対して課税されます。しかし、通常は、売却した時に日割り計算をして精算します。引渡し日の前日までの分を売主さま側負担、引渡し日以降からの分を買主さま側負担とすることが一般的です。
●マンションの管理費・修繕積立費などの精算金
マンションの管理組合に支払う管理費や修繕積立費なども固定資産税と同じように日割り計算をして精算することが一般的です。こちらも、引渡し日前日までの分を売主さま側負担、引渡し日以降からの分を買主さま側負担とすることが一般的です。
マンション売却の控除や特例
マンションを売却して譲渡益が出ると、短期譲渡所得であれば40%近くを、長期譲渡所得でも 20%もの高い税率で所得税などを支払わなければいけなくなります。しかし、マンションなどの不動産売却の譲渡所得に対しては、いくつかの控除や特例が用意されています。節税対策に利用できる控除や特例には次のようなものがあります。●3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、マイホームを売却した時の譲渡所得から3,000万円が控除されるというものです。譲渡所得が3,000万円以下の場合は、譲渡所得が発生しません。
●買い替え特例制度
こちらの特例はマイホームを買い替えたときに利用できる特例です。こちらの特例を利用すると、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができます。新しく購入したマイホームを将来売却する時に、その時の譲渡所得に対する課税と合算して課税されます。
譲渡所得に対する課税を免れられる方法ではありませんが、新しく購入するマイホームを今後手放すつもりがない場合には有効な税金を減額する方法です。
●10年を超えて保有するマイホームを売ったときの軽減税率の特例
10年を超えて所有していたマイホームを売却した場合には、所得税の課税率を通常の長期譲渡所得の税率よりも軽減できる特例です。通常の長期譲渡所得の税率は15%ですが、こちらの特例を適用すると、6,000万円までの税率が10%に軽減できます。所得税、住民税、復興所得税の合計は次のようになります。
・6,000万円までの場合:14.21%
・6,000万円を超えた場合:6,000万円未満の部分の譲渡所得14.21%+6,000万円を超える部分の譲渡所得20.315%
マンション売却の費用に関する注意点
マンション売却の費用については、いくつか注意しなければいけない点があります。注意しなければいけない点については次のようなものがあります。
●確定申告はしたほうがいいのか
譲渡所得がプラスになる場合には、売却の翌年の2月から3月の確定申告期間に確定申告をしなければ納税できません。確定申告をしないと、税務署から指摘されて延滞税や重加算税が加算されてしまいます。ただし、譲渡所得がマイナスの場合には確定申告は必要ありません。
また、控除や特例の申告は確定申告で行います。確定申告をしないと、本来利用できたはずの控除や特例を利用できなくなってしまい、納税額が高額になってしまいます。
長期譲渡所得に該当し、居住者用不動産の譲渡所得がマイナスになる場合には、一定の要件を満たす場合に限り、確定申告をすることで給与所得や事業所得と損益通算できます。給与所得や事業所得のプラスをマンション売却のマイナスで補填して、所得税や住民税を減額できます。給与所得や事業所得のある方は、マイナスになった場合でも確定申告をすることをお勧めします。●控除や特例と住宅ローン控除が併用できない場合もある
譲渡所得に対する税金を減額するために利用できる控除や特例は、基本的に次に買う家での住宅ローン控除とは併用できないので注意しましょう。売却時の税金を減額する効果を狙った控除や特例の利用よりも、住宅ローン控除を利用した方が良い場合もあります。どちらがいいのかは、あらかじめシミレーションした上で決めましょう。
●広告を出してもらったのに売買契約に至らなかった場合の費用は?
仲介手数料は成功報酬なので、売買契約に至らない場合には仲介手数料を支払う必要はありません。
●買い取りだと仲介手数料がかからないって本当?
買い取りとは不動産会社が購入者を見つけるのではなくて、直接買い取る方法です。仲介手数料とは、売主さま側と買主さま側を仲介するための手数料なので、買い取りであれば必要ありません。
まとめ
マンションを売却すると、この記事の中で見てきたように、さまざまな費用が必要です。また、譲渡所得がプラスになると、所得税や住民税等の納税が必要になる場合もあります。
マンションを売却する時には、売却した金額の全てが手元に残るわけではありません。売却前から必要な手数料や税金も計算した上で、実際にはどのくらいの金額を手元に残せるのかを把握するようにしましょう。