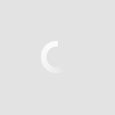国土交通省、空家特措法全面施行に伴うガイドライン発表

目次
全国に約820万戸といわれる空家対策の法律「空家特措法」(空家対策の推進に関する特別措置法)が5月26日から全面施行されました。これに伴い同日、国土交通省は法律の円滑な実施を図るためのガイドラインを発表。大手シンクタンク関係者の1人は「空家特措法の全面施行により空家の活用が促進されて、中古住宅流通の活性化につながる可能性が高い」と述べるなど、空家問題関係者の間で新法への期待が高まっています。
ガイドラインで「特定空家」の基準が明確に
一口に「空家」といっても状態はさまざまで、小規模な修繕を施せばすぐに住める空家から廃屋のような朽ち果てた空家まで存在します。しかし、どんな状態の空家であれ、その存在が周囲に悪影響を及ぼすとなれば、それが個人財産であっても放置できる問題ではないということになります。
そこで空家特措法では「破損等が著しく保安上危険となる恐れのある状態」や「著しく景観を損なっている状態」の空家を「特定空家等」と定義し、市町村による立ち入り調査、指導・勧告、行政による強制執行などを認めています。
こうした措置を円滑に実施するため、ガイドラインでは市町村が「特定空家等」と判断する場合の基準と「特定空家等に対する措置」に関する行政手続きについての考え方を示しています。
まず「特定空家等」の判断については、その基準を(1)放置すれば保安上危険となる恐れがある状態(2)放置すれば衛生上有害となる恐れがある状態(3)適切な管理が行われていないため著しく景観を損なっている状態(4)周辺の生活環境を保全するために放置しておくことが不適切な状態の4つに分類し、それぞれの基準を具体的に以下のように例示しています。
<放置すれば保安上危険となる恐れがある状態>
●建築物の著しい傾斜:基礎の沈下や柱の傾斜など
●建築物の構造耐力の主要部分の損傷:基礎の破損・変形、土台の腐朽・破損など
●屋根、外壁等が脱落、飛散する恐れ:屋根の変形、屋根葺き材の剥落、壁を貫通する穴の発生、屋外階段・バルコニーの腐食・破損・脱落など
●擁壁老朽化による危険性:擁壁表面に水がにじみ出し、流出しているなど
<放置すれば衛生上有害となる恐れがある状態>
●建築物・設備の破損により以下の状態にある場合:
石綿(アスベスト)などが飛散し暴露の可能性が高い、浄化槽の放置・破損による汚物の流出・臭気の発生、排水の流出による異臭発生など
●ゴミ等の放置・不法投棄により以下の状態にある場合:
異臭発生、多数のネズミ、はえ、蚊の発生など
<適切な管理が行われていないため著しく景観を損なっている状態>
●適切な管理が行われていないため景観ルールに適合しなくなっている状態:景観法に基づく景観計画に定める建築物・工作物の形態等の制限に適合しない状態になっている、地域で定められた景観保全に関するルールに適合しない状態になっているなど
●周囲の景観と不調和な状態:屋根・外壁などが汚物や落書きで傷み、汚れたままで放置されている、多数の窓ガラスが割れたまま放置されている、立木等が建築物の全面を覆う状態まで繁茂しているなど
<周辺の生活環境を保全するために放置しておくことが不適切な状態>
●立木が原因で以下の状態にある:
立木の枝等が近隣の道路等にはみだし通行の妨げになっているなど
●空家に棲みついた動物等が原因で以下の状態にある:
動物のふん尿やそのほかの汚物によって異臭が発生している、シロアリが大量に発生し近隣家屋に飛来しているなど
●建築物の不適切な管理が原因で以下の状態にある:
門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れているなどで不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
次に「特定空家等に対する措置」に関する手続きについては、立入調査などの事前準備→空家所有者への助言・指導→空家所有者への勧告→空家所有者への命令→空家除去の行政代執行(除去費用は空家所有者に請求)の順を追って進めるよう市町村長に求めています。
勧告の実施に際しては「固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを告知する」と定めています。これは税制上の優遇措置の対象からの除外を意味しており、相当な効果があるものとみられています。
というのも住宅用地に適用される特例措置として、固定資産税の課税標準が小規模住宅用地(200平米以下)は6分の1に、一般住宅用地(200平米以上)は3分の1に減額されています。これが市町村長の勧告を受けると、固定資産税額がそれぞれ6倍、3倍にはね上がる形になるからです。
また、都市計画税の課税標準も小規模住宅用地は3分の1に、一般住宅用地は3分の2にそれぞれ減額されていますが、こちらの税額も大幅に急騰することになります。こういった措置は「市町村長の助言・指導の段階で、特定空家と認定されない状態に修繕するか解体してさら地にしたほうが得との判断が空家所有者に生まれる」(大手シンクタンク関係者)と期待されています。
「特定空家」を資産化するサービスも
日本国内の空家がここまで増加したのは「新築信仰が強く、中古住宅を資産として整備する意識が希薄だったこと。加えて国が景気浮揚策として新築住宅建設を促進してきたため、中古住宅の流通市場が未成熟のまま置かれてきた」(不動産業界関係者)のが背景といわれています。
しかし、今年6月からは国土交通省が「不動産総合データベース」の試行運用を開始するなど、最近は国も中古住宅流通市場の整備促進に努めています。不動産業界も大手各社が独自の中古住宅品質保証サービスを展開するなど、中古住宅流通市場の活性化に取り組んでいます。
空家特措法の全面施行は、こうした動きを後押しするものとみられています。つまり「空家は放置すれば社会のお荷物、修繕して賃貸などに活用すれば資産との意識転換を空家所有者に促す動機になる」というのが不動産関係者の見方です。
このため、民間でも同法施行にタイミングを合わせたかのような「空家の資産化サービス」が広がりつつあります。例えばある大手住宅会社は昨年11月から分譲マンションや戸建て住宅の空家を巡回して清掃や点検を行い、空家の現況を所有者に報告するサービスを開始しました。別の住宅会社も今年5月から同様のサービスを開始しています。また、空家の管理受託や再生事業の開始を予定する会社もあります。これからは「空家も資産活用の原資」といわれる時代になるかもしれません。