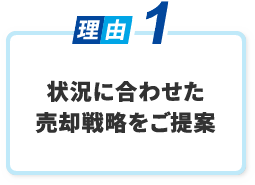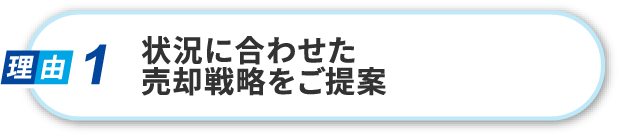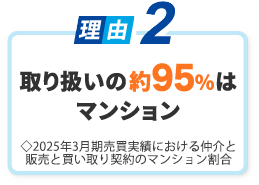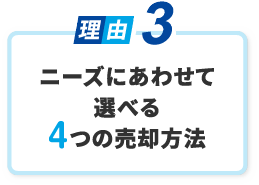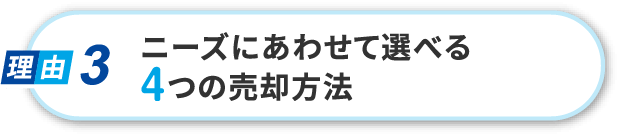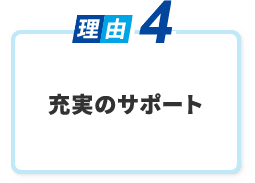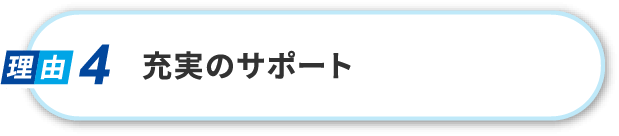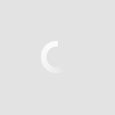【税金シミュレーション】不動産売却時の税金計算方法は?具体例や税金を減額するポイントを解説

先読み!この記事の結論
- 不動産売却時にかかる所得税・住民税と計算方法がわかる。
- 不動産売却をした際に使える控除や特例についてもご説明。
- 実際の譲渡所得についてのシミュレーションのほか、不動産売却でかかるその他の税金について。
こんな悩みの人にピッタリ
- 不動産売買の際にかかる税金について知りたい方
- 所得税の計算方法について知りたい方
- 不動産売却をしたが、控除や特例について、税金を減額させる手続きの方法について知りたい方
目次
不動産売却時にかかる所得税とは
不動産売却をする際、どのような税金がかかるのでしょうか。今所有している不動産が「いくらで売れるのか」も非常に重要ですが、売却前の段階から支払わなければいけない税金について知っておきたいものです。今回は、不動産売却時に支払わなければならない税金とその計算方法、そして税金を少しでも安くする方法をご紹介していきます。
所得税等とは
所有している不動産を売却して、譲渡益が出る場合があります。この場合、発生した譲渡益に対して一定の割合で税金がかかります。この税金の内訳は、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」です。不動産を売却して譲渡益が出ていない場合、これらの税金は一切かかりません。売買した不動産が土地のみであれば、シンプルに買った時の金額と売った金額を比較すればよいのですが、マンションなど建物が購入金額に含まれる場合は注意しましょう。建物は年数が経つごとにその価値が減っていきます。その減価分を耐用年数にわたり分割して費用化することを減価償却といいます。不動産で物件を買った金額を計算する場合、この減価償却を考慮した上で計算します。計算方法について見ていきましょう。
不動産売却にかかる所得税等の計算方法
不動産を売却した際にかかる所得税等の求め方は、かんたんに説明すると
「不動産売却にかかる税金=利益(譲渡所得)×税率」
という計算式で算出できます。このそれぞれの項目、「利益(譲渡所得)」及び「税率」についてもご説明していきます。
①利益(譲渡所得)の求め方
計算式で表すと、「利益(譲渡所得)=不動産を売却した金額-(買った金額+売却にかかった費用+特別控除額)」となります。この4つの要素についてもかんたんに解説していきます。
・不動産を売却した金額
こちらはシンプルに、売却によって得られる金額です。基本的に、売買契約書には金額の記載がないため忘れがちな金額「固定資産税・都市計画税の清算金」を含めた金額が売却金額となります。固定資産税はその年の1月1日の時点で所有している人が税の請求をされるため、年の途中で売買の取引をした場合、所有期間に合わせて固定資産税・都市計画税を按分し、買主さま負担分を買主さまから受け取る必要があり、これを固定資産税・都市計画税の清算金といいます。忘れずに収入金額として含めましょう。
・買った金額(不動産を購入した金額)
取得費、とも呼ばれるものです。購入代金(建築価格)や仲介手数料、契約書の印紙代など、その他様々な費用が含まれています。不動産には土地と建物がありますが、先ほどもご説明した通り土地の売買の場合は減価償却という考えがないため、そのまま購入代金等が買った金額(取得費)となります。
建物の場合は「建物の取得費」=「建物の購入代金等」-「減価償却費」で求めます。
そして、この減価償却費はどのように求めるのかというと、
「減価償却費」=建物の購入代金等×0.9×償却率×経過年数となります。
償却率については木造建築や鉄筋コンクリートなど建物の素材によって数値が変わってきます。経過年数については、6カ月以上は1年として計算し6カ月未満は切り捨てで算出します。買った時期が昔すぎて金額がわからない、という場合は売った金額の5%を取得費としてみなすこともできます。
・売却にかかった費用
不動産を売却する際に、実際にかかった費用のことをいいます。主に、売却時に不動産会社に支払った仲介手数料、売買契約書に貼付ける印紙税などです。固定資産税・都市計画税や修繕費用など、不動産を所有している間にかかった物件を維持する費用は含まれませんので注意しましょう。
・特別控除額
要件を満たしていれば、所得税等を計算する際に譲渡益から控除することができます。様々な種類の控除がありますが、主要な控除の内容については後ほど説明します。
②所有期間に準じた税率を譲渡所得にかける
利益(譲渡所得)を求めることができたら、あとは税率をかけるだけで所得税等の金額が求められます。所有期間が5年以内の場合(短期譲渡取得)は39.63%(所得税等30.63%、住民税9%)、5年超の場合(長期譲渡取得)は20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)となります。
不動産を売却して譲渡益が出た場合、自分で所得税等の計算を行い、確定申告と納税を自主的に済まさなければなりません。放置したままで、税務署から指摘されペナルティを課せられる可能性もあります。譲渡所得の申告については、まずは税理士に相談することも一つの方法でしょう。
不動産売却で使える控除や特例
不動産を売買するときに所得税等が発生する場合、少しでも支払う税金を減額したいと多くの人が考えています。ここでは不動産の所得税等を少しでも減額する方法をご紹介します。
国が定めている特例や制度を着実に適用することがいちばんの方法となります。具体的な方法をご紹介していきます。
控除
1.3,000万円の特別控除
所有していた不動産を売却し、利益が出た場合は以下のときに控除されます。
・自分たちが住んでいた自宅を売却した場合
・相続した家(空き家)を売却した場合
要するに、譲渡益が3,000万円までであれば税金は一切発生しない、というものです。ただし、適用を受けるための要件があるため、該当する場合は国税庁のサイトなどで詳細を確認してみましょう。
2.軽減税率の特例
所有していた不動産を売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が10年を超えている場合は、1で紹介した3,000万円の特別控除の特例を適用した上での課税長期譲渡所得金額に対し、軽減された税率で税額を計算することができます。
3.買い替えの特例
不動産を売った年の前後3年の間に自宅の買い替えをした場合、譲渡で発生した利益の課税を先に延ばすことができる特例です。これを適用させるにはいくつかの要件があり、譲渡価格が1億円以下、所有期間が不動産を売った年の1月1日時点で10年以上、居住期間10年以上などです。
ただし、「買い替えの特例」は1.3,000万円の特別控除の特例 および 2.軽減税率の特例とは、併用できません。どちらかを選択することになります。
税金シミュレーション
では実際に数値を交えて、どのくらいの税金がかかるのかを見ていきましょう。
事例
・パターン① 所有年数5年超の土地売却(長期譲渡取得適用の場合)
売却価格 50,000,000円
譲渡時諸費用 2,000,000円
取得価格 35,000,000円
取得時諸費用 1,500,000円
売却価格50,000,000円-(譲渡時諸費用2,000,000円+取得価格35,000,000円+取得時諸費用1,500,000円)=譲渡所得11,500,000円
所得税+住民税:譲渡所得11,500,000円×20.315%(長期譲渡所得の適用)=2,336,225円
・パターン② 所有年数5年以内の土地売却(短期譲渡取得適用の場合)
売却価格 50,000,000円
譲渡時諸費用 2,000,000円
取得価格 35,000,000円
取得時諸費用 1,500,000円
売却価格50,000,000円-(譲渡時諸費用2,000,000円+取得価格35,000,000円+取得時諸費用1,500,000円)=譲渡所得11,500,000円
所得税+住民税:譲渡所得11,500,000円×39.63%(短期譲渡所得の適用)=4,557,450円
・パターン③ 3,000万円特別控除を利用する場合
諸経費を含め35,000,000円(諸経費含む)で購入した土地を40,000,000円で売却したとします。所有期間は8年間。譲渡費用は3,000,000円かかったとします。
なお、土地の場合は、適用要件が追加されるので、注意が必要です。追加要件は下記。
・家屋を取り壊してから譲渡契約締結までに敷地を貸駐車場などにしていないこと。
譲渡所得【40,000,000円-(35,000,000円+3,000,000円)-30,000,000円】がマイナスになるため、所得税+住民税(復興特別所得税含む)は0円となります。
不動産売却でかかるその他の税金
不動産を売却した際には、所得税以外にもかかる税金があります。把握しておいて損はないでしょう。
税金
・印紙税
不動産売買契約書に限らず、契約時に貼付する収入印紙に支払う税金のことを印紙税と言います。収入印紙を貼り付けし、消印することで、納税するというものです。売主さまと買主さまで1通ずつ契約書を作成する場合は2枚必要です。印紙税は課税対象の文書にかかるので、一定の契約書や受取書、領収証などにもかかる場合があります。印紙税は、2022年の3月31日まで軽減税率が適用されており、文書に記載されている金額が、500万円超1,000万円以下の場合は5,000円、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円がかかります。
・登録免許税
不動産の登記にかかる税金です。売買の際の登記には、「所有権移転登記や抵当権設定時登記」と「抵当権抹消登記(抵当権設定がある場合のみ)」があります。登録免許税は、売買をするときは、法律上売主さまと買主さまの双方で連帯して納税義務を負うよう取り決められています。売主さまが「抵当権抹消の登記費用」を、買主さまが「所有権移転や抵当権設定時の登記費用」を納めるのが一般的です。
不動産売却にかかる税金を減らすには
所得税を軽減させる特例や軽減税率のほかに、不動産売却にかかる税金を減らす方法はあるのでしょうか?売却時の税金を減額するためには主に、譲渡所得(不動産売却で利益に相当する部分)を小さくする、特例を活用する、2点がポイントとなります。これまでにご紹介してきた内容以外で有利になりそうなものをご紹介します。
ポイント
・2009年、または2010年中の土地の取得ではないか確認する。
2009年及び2010年に取得した土地を、所有期間が5年を超える時点で売却した場合、土地の譲渡所得において1,000万円特別控除されるという特例があります。2009年に取得した場合は2015年1月1日以降、2010年に取得した土地等については2016年1月1日以降の売却で適用となります。この特別控除を適用した場合、譲渡所得は次のように計算されます。譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用+10,000,000円)
この特例は、居住用財産の3,000万円の特別控除などの他の特例とは一緒に適用することができないものとなります。3,000万円の特別控除等を適用できないことが判明した場合には、念のため土地の取得が2009年または2010年ではないか、確認してみてください。
・売却のタイミングを見計らう
不動産は、税率が下がったタイミングで売却することも税金の減額ができます。譲渡所得は、税率が長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なります。所有期間が5年を超えたタイミングで売却すると税率が低くなるため、税金を減額することができます。居住用財産においては、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例があります。つまり3,000万円の特別控除を適用しても譲渡所得がプラスとなる場合には、所有期間が10年を超えたタイミングで売却すると税金を減額することができます。
不動産売却後は確定申告の準備を
所有していた不動産を売却して利益が出た場合、確定申告をして税金を納めなければいけません。損失が出た場合は確定申告の必要はありませんが、マイホームの売却は税金の減額を考えて確定申告したほうが良い場合があります。不動産の譲渡所得は分離課税ですので、本来は給与所得などその他の所有と損益通算することはできませんが、マイホームの売却の場合は特例があり、一定の条件に該当すると確定申告をすることで売却損失とその他の所得を損益通算して、課税額を減らすことができます。
不動産売却によって利益や損失が出た際の確定申告には、10点前後の書類が必要となります。手間がかかるように感じるかもしれませんが、必要書類のほとんどは不動産の取得時、売却時にそろえたものになりますので、大切に保管してさえいればすぐに準備ができるでしょう。確定申告書用紙や譲渡所得内訳書の用紙は税務署ですぐにもらうことができます。確定申告は売却した次の年の2月~3月に行うことができますので、不動産の売買をした方は早めに準備しておきましょう。
まとめ
不動産売却時にかかる所得税・住民税について、計算方法、税金を減額させるのために適用できる特例や方法についてご紹介してきました。不動産の売買は、売ったら終わり、購入したら終わり、ということはなく今回のような税金がらみの申請や確認事項が必ずあると認識しておきましょう。いざ売買をするとなったときにも、安心して対応することができます。